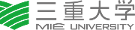産学官連携を実施する先生に知っていただきたいこと > 共同・受託研究を実施するとき
学生を参画させてよいか、参画にあたって何らかの制限があるかなど、事前に相手先と相談してください。
その際、相手先において、現場の研究者と契約部門との間で見解が異なる例もありますので、可能であれば、契約部門の見解も確認してもらうことをおすすめします。
以下の点にご注意ください。
共同・受託研究契約の締結には外部資金等委員会による受入審査での承認が必要ですが、提出いただいた回答書に基づいて利益相反状態等を点検した上で審査を実施しますので、迅速な手続きのために余裕をもった提出へのご協力をいただきますようお願いいたします。(共同研究及び受託研究申込時における利益相反の事前確認について)
また、国立大学法人の役職員は「みなし公務員」ですので、寄附金の受入れが何らかの「便宜供与に対する見返り」と捉えられると、収賄罪に問われる可能性もあります。
契約の相手先が日本の法人等であっても、研究成果が外国の法人等(親会社、関連会社等)と共有されることが契約書に明記されていれば、同様に審査が必要になります。
内容によっては経済産業大臣への許可申請が必要になることもありますので、余裕をもって提出してください。
倫理審査委員会承認後の契約締結・研究開始となりますので、ご注意ください(契約手続きと倫理審査の手続きはどちらも時間を要しますので並行して進めることは可能です)。
ただし、相手方との契約交渉を通じて修正された場合もありますので、必ず契約書の確認をお願いします。
また、「国立大学法人三重大学産学官連携における秘密情報管理規程」により、研究代表者は「秘密情報管理責任者」となりますので、秘密情報の適切な管理をお願いします。
契約書第18条(三重大学のひな形通りに締結された場合)に記載されている期限のご確認をお願いします。
学生を共同研究等に参画させることは、当該学生にとって先進的研究に従事する機会が与えられる一方で、場合によっては法的義務やリスクを負わせることにもなります。
参画させる場合は、「共同研究等への学生参画にあたっての確認書」に従って、それらを学生に説明いただくとともに、学生の同意を得てください(その際、秘密保持の期間について改めて確認してください)。
学生からの同意が得られた場合であっても、当該学生に必要以上の秘密情報にアクセスさせない等、指導にあたっての十分な配慮をお願い申し上げます。
また、契約の際に相手先から、特定類型該当者への対応を義務として契約書に明記することや、特定類型該当者の参画の有無の報告を求められるケースが増えており、正確な情報把握を行うため、「特定類型該当性に関する申告書」も提出いただきます。
(参考)「みなし輸出」管理(学内制限)
これらの書類を一つのファイルにまとめていますので、印刷して様式部分に必要事項を記入し、社会連携チームに学内便で提出してください。
※学位研究のテーマとする学生のみで結構です。アルバイト等の研究補助者については不要です。共同研究等への学生参画にあたっての確認書(Confirmation form for student participation in joint research)
特許を出願しようとする前には、必ず「知的財産届出書」を提出してください。
先に論文・研究発表を行ってしまうと、新規性喪失により特許を受けることができなくなるので、発表よりも前に出願を済ませておく必要があります。
発表(公表)日より1か月前までに、届け出くださいますようお願いいたします。 また、共同研究等相手方から、相手方による単独での特許出願や単独の特許にしたい旨の希望の連絡を受けた場合はご一報ください。
そのとき、本学の名称を使用する場合は、必ず事前に本学の審査を受け、承認を得る必要があります。
大学は学術研究を行う機関であり、製品・サービスに「お墨付き」を付与する機関ではありません。
学術研究の結果は、長い時間軸で考えると「正しくなかった」ということも発生する可能性があります。
「大学がお墨付きを与えている」「大学が保証している」「大学が営利機関の宣伝を行っている」ような印象を社会や消費者に与えると、何か問題が発生したときに信用問題に発展し、大学や先生が訴えられてしまうおそれもあります。
そのため、
まずは、相手先から「プレスリリース時における三重大学名称使用願」を本学広報室に提出いただく必要がありますが、審査には2週間程度を要しますので、お早めのご対応をお願いいたします。
共同・受託研究を実施するとき
- 共同研究・受託研究を実施する前に
- 学生を参画させようとする場合について
- 利益相反・利益供与について
- 相手先が外国法人等の場合の注意
- 人を対象とする研究の場合の注意(倫理審査委員会対象案件)
- 共同研究契約・受託研究契約を締結した後に確認・注意していただきたいこと
- 秘密の保持
- 研究成果の公表
- 学生を参画させる場合の注意
- 研究成果が出たときに注意していただきたいこと
- 特許を出願するときの注意
- 新製品・新サービスを紹介するときの注意
1. 共同研究・受託研究を実施する前に
学生を参画させようとする場合について
学生の参画可否に関する相談
共同研究・受託研究に学生を参画させることは、先進的研究に従事させるという貴重な教育機会を与えることに繋がりますが、研究テーマによっては、学生の参画を相手先から制限されることがあります。学生を参画させてよいか、参画にあたって何らかの制限があるかなど、事前に相手先と相談してください。
その際、相手先において、現場の研究者と契約部門との間で見解が異なる例もありますので、可能であれば、契約部門の見解も確認してもらうことをおすすめします。
参画させようとする学生が相手方の従業員・職員でもある場合(社会人学生等)の注意
同一人物が「相手方の研究者」の立場と「本学の学生」の立場を兼ねてしまうと、研究倫理、利益相反、成果帰属などの問題が発生しますので、次の点に留意してください。- 「本学の学生」の立場のみでの参画とする。(共同研究契約書等においても、相手方の研究担当者・研究協力者から名前を外す)
- 学位論文のテーマ・内容が、相手方の直接的な営利目的にならないようにする。【研究倫理】
- テーマ・内容を、特定の製品・事業等に限定されない一般的なものにする。
- 研究成果を公表する際は、「本学と相手先の両方の身分を持っていること」「共同研究・受託研究の成果であること」を開示する。【利益相反】
- 「共同研究・受託研究の中で学生が創出した知的財産は本学に帰属する」ことを明確にしておく。【成果帰属】
利益相反・利益供与について
共同研究等の産学官連携活動は大学の社会貢献の一環ですが、一方で企業等と経済的利害関係を持つことになるため、適切に実施されていないと、大学の教育・研究活動に悪影響を与えているとの指摘を受けかねません。以下の点にご注意ください。
研究インテグリティに係る回答書
共同・受託研究を行う前の手続きとして、「研究インテグリティに係る回答書」を提出してください。共同・受託研究契約の締結には外部資金等委員会による受入審査での承認が必要ですが、提出いただいた回答書に基づいて利益相反状態等を点検した上で審査を実施しますので、迅速な手続きのために余裕をもった提出へのご協力をいただきますようお願いいたします。(共同研究及び受託研究申込時における利益相反の事前確認について)
- 研究インテグリティに係る回答書 2025-10-1
- ファイルを三重大学Moodleで提出してください。Moodleでの提出手順
- ※メールでは本人認証ができないので受け付けられません。
- 研究期間中に回答内容に変更があった場合は、修正版を提出してください。
- 確認書中の用語の定義については、研究インテグリティ用語集を参照してください。
共同研究の相手方から寄附金を受け入れる場合の注意
共同研究費と寄附金のそれぞれの使途を明確にし、共同研究のためだけに使用する経費に寄附金を充てないようにしてください。また、国立大学法人の役職員は「みなし公務員」ですので、寄附金の受入れが何らかの「便宜供与に対する見返り」と捉えられると、収賄罪に問われる可能性もあります。
その他、「これは利益相反・利益供与にあたるのでは?」と心配されることがございましたらお気軽にご相談ください。
相手先が外国法人等の場合の注意
相手先が外国の法人等の場合、安全保障輸出管理の審査が必要になりますので、「安全保障輸出管理チェックリスト(国際共同研究)」を提出してください。契約の相手先が日本の法人等であっても、研究成果が外国の法人等(親会社、関連会社等)と共有されることが契約書に明記されていれば、同様に審査が必要になります。
内容によっては経済産業大臣への許可申請が必要になることもありますので、余裕をもって提出してください。
- 国際共同研究を開始する場合|安全保障貿易に係る輸出管理
- 安全保障輸出管理チェックリスト(国際共同研究)を社会連携チームにメールで提出してください。
- 複数の教員が参画する場合、研究代表者だけでなく参画する教員全員が手続きを行う必要がありますので、研究代表者から他の参画教員に伝えてください。
人を対象とする研究の場合の注意(倫理審査委員会対象案件)
人を対象とする研究については倫理審査委員会に諮り、承認を得る必要があります(倫理審査委員会に関するお問合せ・手続きは所属部局の総務担当(医学系研究科・医学部は研究支援室)にお願いします)。倫理審査委員会承認後の契約締結・研究開始となりますので、ご注意ください(契約手続きと倫理審査の手続きはどちらも時間を要しますので並行して進めることは可能です)。
2. 共同研究契約・受託研究契約を締結した後に確認・注意していただきたいこと
秘密の保持
秘密保持期間は、三重大学のひな形通りに契約が締結された場合、第15条・第35条2により、契約終了後も2年間有効となっています。ただし、相手方との契約交渉を通じて修正された場合もありますので、必ず契約書の確認をお願いします。
また、「国立大学法人三重大学産学官連携における秘密情報管理規程」により、研究代表者は「秘密情報管理責任者」となりますので、秘密情報の適切な管理をお願いします。
研究成果の公表
共同・受託研究によって得られた研究成果、その他の技術情報を公表等しようとする場合は、相手方に事前に通知する必要があります。契約書第18条(三重大学のひな形通りに締結された場合)に記載されている期限のご確認をお願いします。
公表等をしようとする日の〇〇日前までに相手方に通知する。
学生を参画させる場合の注意
学生は教育を受けている立場であり、契約書における「研究担当者」「研究協力者」にはなりえません。(※注・社会人学生については例外がありえます)学生を共同研究等に参画させることは、当該学生にとって先進的研究に従事する機会が与えられる一方で、場合によっては法的義務やリスクを負わせることにもなります。
参画させる場合は、「共同研究等への学生参画にあたっての確認書」に従って、それらを学生に説明いただくとともに、学生の同意を得てください(その際、秘密保持の期間について改めて確認してください)。
学生からの同意が得られた場合であっても、当該学生に必要以上の秘密情報にアクセスさせない等、指導にあたっての十分な配慮をお願い申し上げます。
また、契約の際に相手先から、特定類型該当者への対応を義務として契約書に明記することや、特定類型該当者の参画の有無の報告を求められるケースが増えており、正確な情報把握を行うため、「特定類型該当性に関する申告書」も提出いただきます。
(参考)「みなし輸出」管理(学内制限)
これらの書類を一つのファイルにまとめていますので、印刷して様式部分に必要事項を記入し、社会連携チームに学内便で提出してください。
※学位研究のテーマとする学生のみで結構です。アルバイト等の研究補助者については不要です。
共同研究等への学生参画にあたっての確認書(Confirmation form for student participation in joint research)
特定類型該当性に関する申告書(Declaration concerning applicability of a specific category)
- 和文様式 2025-11-4
- English form 2025-11-4
- 研究代表者と学生は写しを保管してください。
その他
外国人の研究員を雇用する場合は、安全保障貿易に係る輸出管理の手続きを行ってください。3. 研究成果が出たときに注意していただきたいこと
特許を出願するときの注意
研究成果から発明が生まれた場合、その権利(特許)は、共同研究であれば三重大学・相手方の双方に、受託研究であれば原則として三重大学単独の帰属となります。特許を出願しようとする前には、必ず「知的財産届出書」を提出してください。
先に論文・研究発表を行ってしまうと、新規性喪失により特許を受けることができなくなるので、発表よりも前に出願を済ませておく必要があります。
発表(公表)日より1か月前までに、届け出くださいますようお願いいたします。 また、共同研究等相手方から、相手方による単独での特許出願や単独の特許にしたい旨の希望の連絡を受けた場合はご一報ください。
新製品・新サービスを紹介するときの注意
研究成果から生まれた新製品や新サービスを、相手先がWebサイト、カタログ、プレスリリース等にて紹介したいということがあります。そのとき、本学の名称を使用する場合は、必ず事前に本学の審査を受け、承認を得る必要があります。
大学は学術研究を行う機関であり、製品・サービスに「お墨付き」を付与する機関ではありません。
学術研究の結果は、長い時間軸で考えると「正しくなかった」ということも発生する可能性があります。
「大学がお墨付きを与えている」「大学が保証している」「大学が営利機関の宣伝を行っている」ような印象を社会や消費者に与えると、何か問題が発生したときに信用問題に発展し、大学や先生が訴えられてしまうおそれもあります。
そのため、
- 利益相反状態の有無
- 営利機関との関係について、事実のみが記載されているか?
- 第三者から「特定の営利機関に肩入れしている」と見られない様な記載になっているか?
まずは、相手先から「プレスリリース時における三重大学名称使用願」を本学広報室に提出いただく必要がありますが、審査には2週間程度を要しますので、お早めのご対応をお願いいたします。